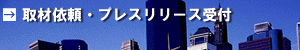阪村氏のねじと人生
印度(インド) 1
念ずれば花ひらく、求めよ、さらば与えられん―と言っても「蒔かぬ種は生えぬ」である。
タンポポの種が、沃野に落ちるか、コンクリートの道路に落ちるかを心配するより、先ずその種を風に乗せて飛ばすことである。
独立した昭和22年(1947)は、商社もどこで何がつくられ、どこで何がうれるかも、全く分からない時代であった。
そのため“阪村機械”の手書きのカタログは、喜んで各地へばら撒いてくれた。
その1つが、遠く印度で実を結んだ。英国から独立した印度の実業家マンデリア氏が、軽工業育成のために、ねじ、釘ピンの製造を計画した。タタ製鉄の源泉から、酸洗、石炭コーティング、伸線、焼鈍、ヘッダー、ねじ切り、針ピンの研磨、焼入れ、テンパー、そしてラッピングのプラントを請負ってほしいとの依頼である。
商社は日棉実業であったが、単体の機械は見積もれても、全体のプラントとなるとどこも手をつけないので、友人の中井からその話が持ちこまれた。
早速、工業学校で覚えた鳥瞰図にて、立体的にプラント図を作成し提出したところ、正式契約となった。恥ずかしい話だが、英語のウッドスクリュー(木ねじ)は、印度の硬いチーク材を原料とする“木製”ねじ位にしか考えておらず、慌てて上京し高橋螺旋の高橋保蔵氏より「木ねじ」についていろいろと教えて頂いた。
ヘッダーは、関根鉄工所の一度打ヘッダーより、最近評判の良い東京自動機の二度打ヘッダーがよい。ねじ切りは切削の自動機で、先の鋭い切り上げについてクシ刃の作り方―等といろいろと教えて頂いた。
高橋氏44歳、阪村22歳の春である。
印度との契約成立により日棉実業の米田課長は、工場も無い阪村に契約金6百万円を支払ってくれた。
そのお金で布施に工場を建てた。やっと自分の工場が出来たのである。
昭和29年(1954)に結婚して妻となった眞島照子を、浜田印刷からスカウトし、女子社員として採用した。
堺税務署に勤務し、結婚支度にと買い整えた着物を一枚、又一枚と売っては協力してくれていた妹(長子33歳で没)の結婚には最高級のブラザーミシンをお祝いに買って恩返しが出来た。
工場が建ち、機械メーカーとして第一歩を踏み出した。しかし機械を作る設備としては、伸線機等の大歯車は、歯切りの会社がないため鋳物のままで組立てていた。軸受は樫の木である。電気炉はニクロム線と制御版、外枠だけ揃え、すべて印度で組立てる事とした。
数十台の出荷を行い、昭和27年(1952)、旅券番号33(民間人では3人目と聞いている)で、38人乗りの英国機にて、アメリカ占領地の沖縄を経由し、印度へと旅立った。
当時は日本の円もドルも国際通貨でなく、英国のポンドだけであった。印度とは国交がなく、日本の大使館もなく、無一文で単身の乗り込みである。
しかし、生活は天国であった。
初めて味わうパン、バター、砂糖、すべてが口の中でとろけ“この世にこんなに美味しい物があったのか”と夢心地であった。そしてホテルではまた、それがいくら食べても飲んでも無料であるというのには驚いた。
「貧しき者よ、汝は幸なり」
イエスの言葉であるが、なんで貧しいものが幸なのか、アホか、と思ったが、敗戦国で「もう食うものがない」と、食うや食わずにて必死に生きてきたからこそ、このパンの何ともいえない香りが、こんなにも幸を感じさせてくれるのである。
ヤシの木の上の美しく輝く月を見て「幸」とは何かを考えるゆとりを与えてくれた24歳、印度での誕生日であった。
本紙2004年3月27日付(1927号)掲載。
バックナンバー
- 印度(インド) 1 2007.07.06 金曜日