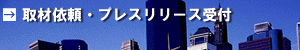「生魚の価値観」
記念すべきこの連載の1回目で、牛生肉のカルパッチョが本来のもので、魚のカルパッチョは日本人シェフが日本の刺身をアレンジしたものと書いた。
若かりし頃の自分がイタリアに初めて行こうと考えた時、地中海の地図を見て、海に囲まれた日本と同じような食文化だろうと安易に想像していた。すなわち、毎日イタリア中どこへ行っても「ペスカトーレ」なのだと。
そしてイタリアの地に立ってみて、その想像は大きく違っていた。身の回りに魚介がほぼ存在しないのだ。例えば、自分が働いていた現地のレストランでも毎日の賄いに魚介類が出ることはまずない。クリスマスの時にオマール海老が特別に出た思い出しかない。日本人が聞いたら驚愕だろうが、彼らは魚介類を食べなくても生きていける、というより食べずに生きているのだ。魚が大好き、という輩にも出会った事がない。
実は最近自分も、イタリア滞在経験が長いからだろうか、日本でも魚介類を積極的に食べなくなった。
日本人は、鰯でもサーモンでも、鯖でも鮪でも、とかく脂の乗っているほうを評価して所望する。
ところが彼らは違う。生で脂のギトギトした魚が苦手なのだ。イタリアの鯖はスリムだし、鰯も脂の白くなった大羽鰯などいない。基本は小さなカタクチ鰯で、塩漬けとしてアンチョビーになるか、酢漬けにするかだ。鮪はオイル漬けにしてツナとしてきた。日本のシーチキンは、彼らがそのルーツなのだ。そして日本人には最も馴染みの薄い、彼ら国民食の干し鱈は基本で、通称「バッカラ」と呼んでいる。大西洋で揚がった鱈を極寒の北欧で乾燥させてから保存食としてヨーロッパ中に流通させる。そのカチカチの乾燥鱈を水でふやかして、塩抜きをして食べるのだ。アンチョビーもツナも干し鱈も彼らにとっては鮮魚という認識は少なく、国民的保存食なのだ。
これが何を意味するかというと、ワインとの相性なのだ。生で脂の乗った青魚を食べるとどうしても生臭くなってしまう。日本人として考えても、若いときは気にならなくとも、経験を重ねてくると寿司にはやはり日本酒が一番しっくり感じるのが本音だ。但し白身魚や貝の握りは塩と柑橘で食べると白ワインやシャンパーニュがよく合うし、漬け鮪や煮穴子には赤ワインもいける。青魚の脂や鮓じめのもの等はさすがに日本酒の力を借りるしかない。ワインではお手上げだ。
本紙2017年12月7日付(2420号)掲載
バックナンバー
- 「生魚の価値観」 2020.03.19 木曜日