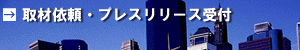「生ハムの見分け方~加工肉の価値(続編)」
日本で馴染みのある生ハムやサラミを「どこで買って食べても、どこの店で食べてもこういう味だよね」と思っていらっしゃる方がいるとすれば、もはやその時点で重症だ。
実は筆者でさえも10年前まではそう思っていたのだから仕方ない。イタリアを30年前から行脚していても、厚労省の食肉に関する諸々の規制などで日本へ輸入させるために使用された多少の酸化防止剤が味をつまらなく(平均的に)させているのだと思い込んでいた。
特にサラミの場合は生ハムと違って一枚肉ではなく、ミンチを詰めて作るため結着肉ならではの雑菌発生のリスクを抑えるために薬品の使用量が増える事となる。数年前に日本の焼肉屋のユッケで残念にも犠牲者が出たが、ユッケにするため生肉を細かく切断する包丁やまな板等調理設備の不衛生さが招いた悲劇であった。それだけ結着肉というものには本来ナーバスになるのだ。ハンバーグも同じで、中がほんのり赤く、肉汁が溢れ出るようなものについては神経質にならざるを得ない。調理器具の衛生や生肉の時点での扱う時間や温度に気を使うのが当たり前なのだ。
欧米は島国日本と違って紀元前から肉を食べ続けている。生肉や加工肉に対する経験値も実績も遥かに高いのだ。ゆえにそれらに対する価値の高さや扱い方も浸透しているのだ。
話は戻って、日本では10年程前まではヨーロッパの比較的大手の生産者からのみ加工肉を仕入れていた。日本で作られてコンビニやスーパーで売られているものよりも断然クオリティは真っ当なのだが、大手ならではのメリットとして世界的に輸出と販売の実績があり、日本への輸入が本格的に始まった時期には小規模生産者では出来ない取引の円滑さが日本の商社にとっても魅力であった。大手ならではのデメリットは材料の食肉も大量に確保するために、その飼育も製品も平均的となる。リスクを減らすのだから味も平均的だ。でも今はちょっと変わってきた。小さな輸入元が、大手にはない、更なる味の個性や職人性を探し求めるようになって来た。すなわち第二次加工肉ブームの兆しである。
健やかに育った血統の良い個体からであれば、誰もが素材の味や価値を際立たせるために、細心の注意を払い、その食味を維持するために添加物は極力使用しない筈だ。これはワインにも言える事だが血統のちゃんとしたブドウで除草剤や農薬等使わず、手間をかけて育てた健全で自信に満ち溢れたブドウからワインを作るとき、添加物を入れたいと思うだろうか?最小限に留めるべきである。その代わりそのワインは健全で神々しく、喜ばしいものになるのだ。値段が高くても、ものが良いというのはこういう事だ。逆を言えば、お値段が安いものは、その安さに自信を持っている、ということになるが、その原価を考えると、企業努力やテクニックだけでは到底補えない程の、原料に差異があるのだろう。(続く)
バックナンバー
- 「生ハムの見分け方~加工肉の価値(続編)」 2020.05.14 木曜日