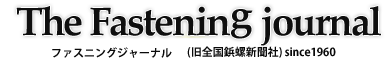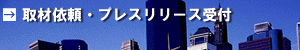ケヴィン山内の英語まめ知識
日本語と印欧語の関係 その(2)
イギリスという日本語は English を日本語読みにしたものだが、そのイギリスのグレイトブリテン島(Great Britain)に、5世紀ノルド人(Viking と解釈しても良いだろう、彼等はAnglo-Saxon人とかチュートン族(Teuton)と呼ばれた)が移住した。北欧のノルド人もグレイトブリテン島の先住民ブルトン(Breton)人も同じ西ゲルマン語族だったので相互理解できたそうで、彼等がイギリスで話したのが Old English(O.E.古英語)である。その O.E.が大幅に変わったのが同じ Viking 出身のノルマン人(但しノルマンディー出身の)ウィリアム1世がイギリスを征服してからである。それを歴史上The Norman Conquest of England ノルマン人のイギリス征服と呼ぶ。
ところでノルマンとかノルドとかノルウェイなど色々「Nor」を使うことばが出てくるがいずれも「北の」の意味である。だからNormanはNorthman ということになる。因みにEngland とはAngloland(アングロ人の土地)から来ている。ノルマン人は早くかViking の名で全世界へ足を伸ばし、フランス北西部へ移住してノルマンディー公国を建国し、コロンブス以前にアメリカ大陸を発見したりもしている。
地中海ではシチリア王国を、そしてロシアへ進出しスラブ人と混血しそこでキエフ公国を作った。また彼等は十字軍に参加したりローマ皇帝の傭兵になったりもした。その後今で言う北欧3国に加えアイスランド、グリーンランドそしてフィンランド人にもなった。
さてフランス北西部のノルマンディー出身のノルマン人はイングランドを制圧し王朝を建てた際、ウィリアム1世は被支配者豪族との間のコミュニケーション手段としてフランス語を公用語として押しつけた。それで大量のフランス語が古英語に流入した。この流入を機会として古英語は中世英語へと移っていく。
次回は現在の英語にいかに多くのフランス語が入っているかを説明しよう。
本紙2010年10月27日付(2164号)掲載
バックナンバー
- 日本語と印欧語の関係 その(2) 2011.06.21 火曜日