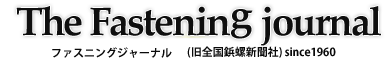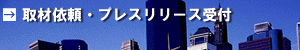ケヴィン山内の英語まめ知識
日本語と印欧語の関係 その(1)
上の図は皆さんに英語に少しでも興味を持っていただきたいと思って書きました。以前の「日本語になった外来語」でも触れていますが、イギリスにフランス語が大量に入ってきた頃の話と併せて少しまとめてみました。
学習院の故大野進教授が「日本語タミル語語源説」を唱え、マスコミの話題をさらったのはついこの間のことです。因みにタミル語はインドの15の公用語の1つでメソポタミアからの語彙が最も多く含まれているドラヴィダ語族の1つです。日本語のルーツがタミル語であるかどうかは別にして、古代メソポタミアのことばがインドを経由して日本に入ってきたのは事実です。
縄文時代にカルターナということばがインドから日本に入ってきた時、縄文人は今の日本人と同様に「r」の発音が下手だったので「ル」が消えて「カタナ」になった話は前に書きました。「切る、切るもの、四角に切られたもの」などの意味を持っていたであろう「カルターナ」は日本語の「刀」になりました。同じように「カルターナ」はヨーロッパ諸国へ伝わりドイツ語のカルテ、ポルトガル語でカルタになりました。つまりインドを出てポルトガルに入った「カルターナ」は、時を経て大航海時代にゲームのカルタとなって日本へ再流入したことになります。そして英語では「カルターナ」「r」と接尾語の「na」が消えて「cut」になり、名詞で「card」になりました。
日本語古語辞典で「刀」を引くと「片刃」と出ていて片方だけの刃の意味なのでしょうがこれはあまりにもこじつけ的で疑問が残ります。日本語の中からしか日本語のルーツを求めようとしない、そして日本の近隣の国の言葉を全然研究しようとしない日本語
学者の勉強不足が原因かと思います。この話は歴史言語学者の故川崎慎治先生が何冊もの著作で、上述のメソポタミアからの由来を発表証明しておられ、やはり日本の言語学者の怠慢を嘆いておられました。私はある日本語古語の教授を訪ねてカルターナの話をしましたら、「刀」の語源をご存知なく、辞書を引いて「片刃」で正しいと言い、その教授は学生に日本語の語源は探ってはいけない、とわざわざプリントを配って語源の勉強をしてはいけないと強く戒めていると私に真顔で言ったので、私は開いた口がふさがらなかったのを今でもよく憶えています。
本紙2010年9月27日付(2161号)掲載
バックナンバー
- 日本語と印欧語の関係 その(1) 2011.05.06 金曜日