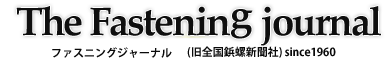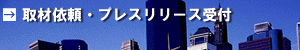ケヴィン山内の英語まめ知識
日本語になった外来語 (10)
時代は更に下り、ヨーロッパの列強から主役の座はアメリカに取って代わり、アメリカは黒船で日本を脅しついに日本を開国させた。
それまでオランダ語を勉強していた日本人が英語の重要性に気が付き、オランダ人から習った英語でイギリス人との会話が成立しなかったという笑えない話もある。
交渉に際し、幕府の通詞達は今までの英語から今度は米語の勉強をしなければならなかった。やがて一般庶民にも米語の影響がじわじわと浸透してきて、耳に聞こえてきた音を綴りも見ずしてそのまま発音することによって、大量の米語が日本語の中へ入ってきた。
消えてしまった言葉はこの際忘れて、今でも元気に生きている単語をいくつか挙げてみよう。
メリケン粉やメリケン波止場などのメリケンはAmericanから、ミシンはmachine、ラムネはlemonade、ビラはbill、トロッコはtruckからだが本来の意味と変わってしまっているみたいで、今はそのままの意味のトラックにもなっている。ゴロはgrounderから、ドロップは菓子のdropだが、同じ綴りで野球のドロップもある。
第二次世界大戦でアメリカが日本へ上陸し占領したことが日本語に米語を源とする単語が多くなった理由となるでしょう。G.H.Q.はGeneral Headquartersで占領軍の総司令部のことだがGo Home Quicklyなどと茶化して言われたりした。
逆にアメリカ兵が日本から持って帰ったことばもある。skibby、skippyは助平から、honchoは日本の兵隊の班長から、Hey,big honcho(どうだい友達、景気はどうだ)と他人に話しかける時などに使うが、英和辞典にも出てこなくなったし、アメリカでも日米戦争の風化とともに少しずつ消えていっているみたいです。
本紙2007年9月27日付(2053号)掲載
バックナンバー
- 日本語になった外来語 (10) 2008.04.18 金曜日