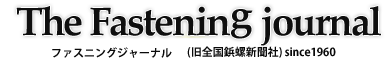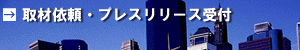ケヴィン山内の英語まめ知識
日本語になった外来語(2)
その(1)で申し上げたように日本語のルーツを辿っていくとインドへ着き、東に辿ると古代シュメールに到着すると言いました。シュメール人は外洋航海術に優れ商人と船乗りの共同体であるドゥーラビーダの人達がインドのモヘンジョダロ遺跡やハラッパ遺跡のある場所に町を作りました。
シュメールには鉱物資源が乏しかったので、彼等は鉱山師として山のある中国へ入りました。中国の学者には漢字は中国人だけによる発明だと頑なに学説を唱えている人もいるようですが、数パーセントの漢字はシュメール人が持ち込んだと言われています。さて鉱山師達の持ち込んだ言葉は一部中国語になりそれが日本にも伝わってきている例をお話しましょう。
シュメール語で金をグシュキンと言いますが頭がとれてキンとなり金という字があてられました。またグシュキンがそのまま日本へ入り金鉱のある場所の地名になりました。その場所は串木野(くしきの)ですが、他の所でも発音が近い名前が残っています。銅はウルドゥーと言い中国ではドゥーだけになり銅があてられました。日本でも銅の事を「あか」と言いますが、このウルドゥーが英語に入りredになりました。
イヴが住んだ楽園はエデンの園と呼ばれています。エデンはヘブライ語ですがこれが中国へ入り頭のエが取れて田という漢字があてられ、日本へも入りそのままデンと発音したり変化してタという読み方が生まれました。ことばって面白いですね。
2005年7月7日付(2009号)掲載
バックナンバー
- 日本語になった外来語(2) 2007.01.04 木曜日